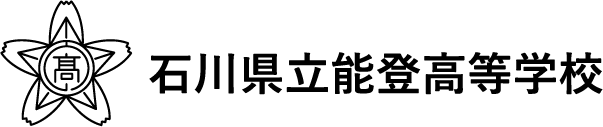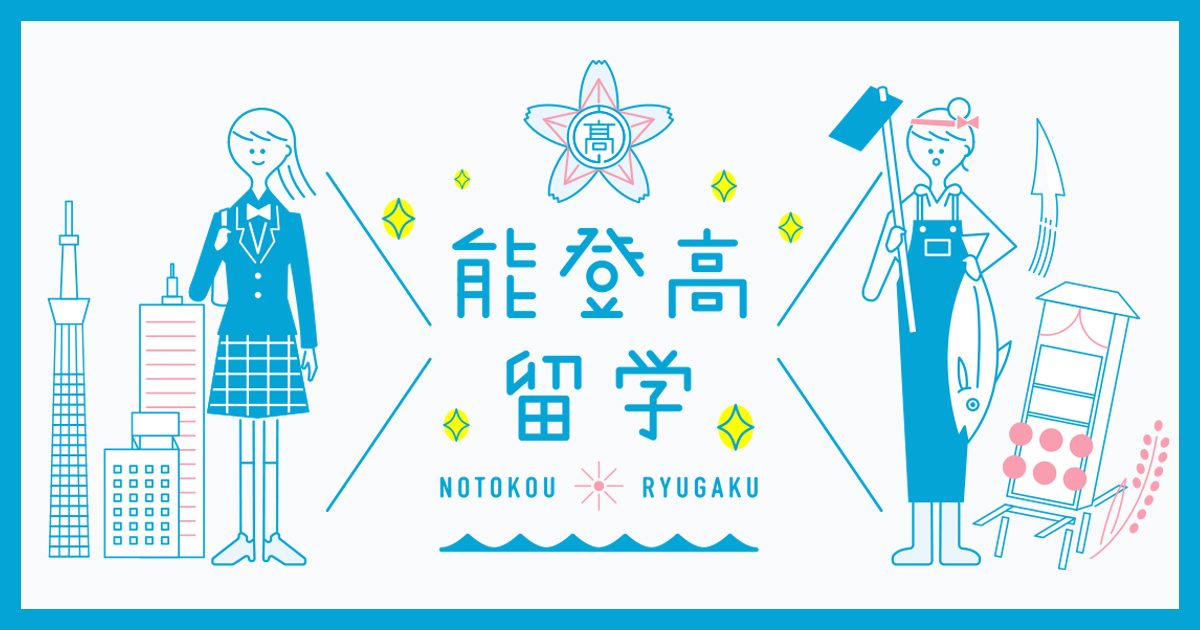7月18日(金)の終業式終了後から7月21日(月)まで有志生徒企画の東北復興スタディツアーが実施されました。
このスタディツアーは今年3月に岩手県立釜石高校の生徒との交流が能登町で行われ、その続編として計画されたものです。
生徒が主体的にイチからこの企画を計画し、メンバーを集い、能登高生7名の参加により実現しました。
7月18日(金)は現地への移動だけで終わり、7月19日(土)から現地視察が行われました。
まず初めに、宮城県石巻市にある日本カーシェアリング協会様を訪問して、カーシェアの観点から復興支援に携わってきた思いや方法などのお話をいただきました。

カーシェア協会様へ訪問
その後は震災遺構として残されている門脇小学校に向かい、震災当時の様子について語り部を行なっている方からお話を伺いました。避難先の高台に実際に登り、津波が来たところや震災前の街と現在の復興が進められている街の比較などについてご説明いただきました。町内会長さんにもお時間をいただき、震災当時から現在までの復興の変遷について地元住民の目線から話していただきました。

門脇小学校の隣の高台避難所へ歩いていく様子
午後からは宮城県女川町役場を訪問し、公民連携室イノベーション課の方から女川町の計画的で若者を中心とした街づくりに関して話していただきました。女川町は津波により壊滅的な被害を受け、ほとんどイチから街を作り直す必要がありました。街を新しく創るという観点で、「人」を大事にする前向きな復興を行なってきた具体的な事例を学びました。

女川町訪問の様子
7月20日(日)は朝一番に岩手県大槌町に向かいました。ここでも、震災が起きた後の様子とその教訓を活かした防災の街づくりについて学びました。大槌町では、海の隣に14mに及ぶ堤防が作られており、実際に登ってみました。海が見えなくなってしまいましたが、津波から街を守ることができる高さであると実感しました。その後は大槌町の街を周っていき、震災の記憶を風化させないための木碑であったり、街並みの中で被害のあった場所などを見て周りました。大槌町中央公民館安渡分館にも訪問し、震災のことについての展示を見て、学びました。

岩手県大槌町の堤防の上で説明を受けている様子
その後は昼にかけて、岩手県釜石市の「いのちをつなぐ未来館」を訪問し、語り部の方のお話を伺いました。釜石での震災当時の様子から現在の復興の過程での課題などのリアルなお話を聞けました。
午後は、岩手県釜石市で防災や震災伝承を行う高校生有志のグループ「夢団」の高校生と、震災伝承の方法や防災に関するゲームを、楽しみながら教えてもらいました。その後、その晩と前日の晩に宿泊させていただいた古民家でBBQを通した交流を行ない、「夢団」のメンバーとの繋がりがより深くなりました。
その当時の様子は、かまいし情報ポータルサイト 縁とらんすにて取り上げていただきました。合わせてぜひご覧ください。

岩手県釜石市で「夢団」の高校生と防災ゲームを通した交流
7月21日(月)朝に釜石高校の生徒と別れの挨拶を交わし、能登に向かい帰宅しました。
ツアーに参加した能登高生はこの4日間で様々な人と出会い、震災・復興に関するたくさんのものを見て、聞いて学んできました。現在はこのスタディツアーでの学びを振り返り、高校生が能登の復興のためにどのようなことができるのかを話し合っています。今回のこの学びを今後、能登の復興にどう活かしていくのか、生徒一人ひとりに期待しています。

能登高校の生徒と「夢団」メンバーの交流